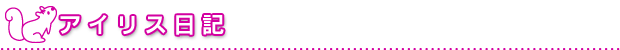| 今年も残すところ1か月 | ||
| 2021/12/03 | ||
|
早いもので、今年も残り1か月となりました。気温がぐっと下がり、冬到来という感じですね。気温が下がり空気が乾燥すると、ウイルスの活動が活発となり、インフルエンザや感染性胃腸炎などの冬の感染症が流行するため、注意が必要となってきます。また、青森県感染症情報センター(11月26日時点)によると、青森県内において、水痘、手足口病が流行しています。手洗い、手指のアルコール消毒、十分な換気、必要に応じて加湿も行うなど、しっかりと感染対策をしていきましょう。
新型コロナウイルスに関しては、日本では全国的にも感染者が減少傾向にあり、青森県内においても、このところは感染者はなしとなっています。しかし、他の国では、再び新型コロナウイルス感染者が増加し、新たな変異株である「オミクロン株」が確認されており、日本においても確認されています。デルタ株より感染力が強く、ワクチンの有効性が弱まる恐れがあるとのことです。「オミクロン株」について、まだ十分に分かっていませんが、オミクロン株が出現したとしても、私たちができる感染対策は変わりません。手洗い、手指のアルコール消毒、3密を避ける、マスクを着用するなど感染対策をしっかりと続けることが大切です。気を緩めることなく感染対策を継続し、元気に年末を過ごしていきましょう。 |
||
| 季節の変わり目 | ||
| 2021/11/01 | ||
|
11月に入りました。最近は、朝晩が寒く、日中は気温が上がって暖かい、という寒暖差の大きい日が続いています。街の木々も赤く色つき、季節の変わり目を感じます。
このところ、全国的にコロナウイルス感染者が減少してきています。県内でも減少傾向で、感染者ゼロの日も出てきました。このことは、ワクチンが進んだおかげであればよいと思います。しかし、海外では、再び感染者の数が増加している国もありますので、まだ、気を緩めず、基本的な感染予防に、気をつけなければと思います。
さて、県内では、感染性胃腸炎が流行してきています。感染症対策として、手洗い・うがいが重要です。また、これからの季節は、インフルエンザにも気をつけなければなりません。これから、段々と寒くなってきますので、体調管理に気をつけて、お過ごしくださいね。 |
||
| 10月からインフルエンザ予防接種が始まります | ||
| 2021/10/04 | ||
|
10月に入り、昼間はまだ汗ばむ日もありますが、朝晩グッと気温が下がり、冷え込むようになりました。季節の変わり目で体調を崩しやすい時期でもあり、これからの季節は、インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症に注意が必要です。
昨年は、例年よりインフルエンザ感染者数が減少傾向にありましたが、今年も、新型コロナウイルス感染症と並行して感染予防が必要です。感染予防には、手洗い、うがい、手指のアルコール消毒、マスクの着用が基本ですが、インフルエンザワクチンも予防に有効です。
10月から各医療機関でインフルエンザの予防接種が始まります。医療機関によって、開始日が異なりますので、かかりつけの医療機関に確認してから予防接種を受けましょう。また、お子さんだけでなく、同居するご家族全員で予防接種を受けるようにしましょう。 ※ご家族(12歳以上の方)で新型コロナワクチンを受けた場合、接種後2週間は、他のワクチン接種は受けられないので注意しましょう。
万が一、インフルエンザに罹ってしまった場合、アイリスは、解熱後24時間経過した日から2~3日間の利用が可能となります。利用を希望される場合には、事前に電話予約が必要になります。なるべく対応させていただきますが、回復期にあたらない場合や定員を超えている場合などはお断りする場合もございます。また、看護師の研修・出張等の日は、アイリスはお休みとなりますので、前もってご了承ください。 |
||
| 9月に入りました | ||
| 2021/09/08 | ||
|
早いもので、もう9月に入りました。お盆過ぎたあたりから、朝晩はとても涼しくなり過ごしやすくなりました。 全国では、コロナの第5波で感染が拡大する中、県内でも先月下旬から、コロナ感染者が増加して、なかなか終息が見えません。ワクチン接種が進み、少しでも終息に向かってくれたらと思います。コロナに加え、これからの時期、体調を崩しやすい時期でもあり、感染症も流行る時期ですので体調管理はしっかりと行い、手洗い、手指のアルコール消毒、マスクの着用、人混みは避けて行動するなど感染対策もしっかりと行っていきましょう。 こんな時には、アイリスに遠慮せずにお電話ください。 熱は下がっているものの、体調がすぐれず、どうしても保育園やこども園に通うには体力が心配…、病院の先生に勧められたという場合などは、なるべく対応していきたいと思いますので、ご利用ください。
|
||
| 熱中症・新型コロナウイルスにご用心 | ||
| 2021/08/06 | ||
|
8月に入りました。外に出ると、サウナに居るかのような暑い熱気に包まれます。外に出る際には、しっかりと暑さ対策をして、無理のない行動をしましょう。また、今の季節は、室内にいても、熱中症に注意が必要です。エアコンで室内の温度を調節して、こまめに水分補給をしましょう。
夏はおいしい果物がたくさんありますが、その中でも私が好きなのはスイカです。水分が多く冷蔵庫で冷やして食べると、とても甘くて美味しいです。旬のものを食べると、季節を実感することができます。
先日、保育関係者向けコロナワクチン接種の2回目を受けてきました。やはり、1回目より副反応は強く出ました。具体的には、38.6℃の発熱と倦怠感、関節痛、接種部位の腫れ・痛み、といった症状がありました。症状は、2~3日位で無くなりました。
新型コロナウイルス感染者数増加により、8月2日から、6都道府県に緊急事態宣言が拡大され、5都道府県には、まん延防止等重点措置が適応されました。私も、これまで以上に感染対策をしっかりと行っていきたいと思います。 |
||
| 新型コロナワクチン | ||
| 2021/07/10 | ||
|
今年に入ってあっという間に半年が過ぎました。このところスッキリしない天気が続いていますね。部屋の中もジメジメして、ついついエアコンをかけすぎてしまいます。 今年は5月頃から、RSウイルスが全国的に大流行しており、五所川原管内においても感染が確認されています。これからの時期は夏の感染症(手足口病、ヘルパンギーナ、プール熱など)の流行も心配されます。 さて、昨年から続く新型コロナウイルスの影響により、各地の夏のイベントは中止を余儀なくされています。東京都では、感染者数が増加傾向にあり、4回目の緊急事態宣言が発令されました。オリンピック開催が2週間後にせまる中、感染拡大がとても心配です。私は、マスクの着用、手指の消毒、なるべく人混みは避けて行動する…など、自分でできる感染予防はしっかりやっています。そして、先日、保育関係者向けの新型コロナウイルスワクチン接種(1回目)を受けてきました。注射したところの痛みや腫れ、ほてりはありましたが、そのほかの副反応は見られませんでした。ほかの接種を終えた方の話では、2回目の方が発熱やだるさなど、副反応が強くでたとのことでした。各自治体では、65歳以上の方のワクチン接種に続いて、若い世代への接種も始まるようです。ワクチン接種は、個人の判断だと思いますが、早くワクチン接種が進み、感染者が減少してほしいと思います。
|
||
| コロナ禍にあって | ||
| 2020/06/27 | ||
|
6月も後半になり、梅雨らしい空模様の日が続いています。花壇や軒下のアジサイも色づき始めてきました。一見、いつもの年と変わらぬ光景ですが、気持ちはどうもすっきりしてきません。2月下旬からの新型コロナウイルス感染症騒動は発生から4か月余りを過ぎましたが、依然として大都市圏を中心に数十人超の感染者が報告され、解消への出口は見えてきません。すっきりしない気持ちはやはり新型コロナウイルスにありそうです。
病後児保育センターみどりの風アイリスだけでなく全国の病後児保育施設・病児保育施設では、今年度、利用者が激減しているようです。一番の理由は「病後児保育事業所で新型コロナウイルスに感染するかもしれないから」だそうです。当センター(アイリス)でも4月からの利用者がこの3ヶ月でわずか10人余りとなっています。月に3~5人しか利用されていないことになります。問い合わせや予約は入るのですが、前日や当日のキャンセルが相次ぎ、スタッフのやりくりにも正直なところ苦慮しています。
東京や札幌など感染が大流行している地域ならまだしも、青森県、とりわけ五所川原地域では新型コロナウイルス感染の心配は、今のところほとんどないといってよいでしょう。でも、その心配から利用希望が減っていることは確かなのかもしれませんが、実はもう一つ、本来はこっちの方が重要だと思うことがあります。それは、新型コロナウイルスへの感染予防に市民のみなさんが気をつけるようになって、他の感染症、例えば感染性胃腸炎やこの時期に多い手足口病などの流行がだいぶ抑えられているということです。これはこの地域だけでなく全国的な特徴のようです。
手洗いやうがいをこまめにする、マスクを着用する、アルコール等で消毒する、むやみに人ごみへ出かけない、静養や栄養に気を付ける…といった感染予防のための日々の生活の変化が、結果的に子どもたちを感染症から守っているということになります。あらためて考えてみても、実はこのことというのは当たり前のようであるものの、本当に大事な予防策なのだと気づかされます。
私たち保育者だけでなく社会も医療も役所も学校も、これまでインフルエンザなどの感染症発生時期には、手洗い・うがいやら手指の消毒やらその重要性を何度となく口にしてきました。でも、実際にはそれらが十分に取り組まれていたかというと答えはNOに近かったかもしれません。ですから、どこそこの保育園や小学校で〇〇〇〇が大流行…そして半月もすると市内全域で大流行ということが珍しくありませんでした。今回のコロナ禍での私たちがとった自衛策・予防策は確かな効果があることを実証してくれたのです。
それでも今回の敵は目に見えないウイルスです。マスクの生地の隙間など全然通り抜けることができます。けれどウイルスは単体で移動するとこはほぼ不可能です。大半が唾液の飛沫に包まれて口から体の外へと出ていきます。その際にマスクは大きな効果があります。飛沫はマスクの目を通り抜けられないからです。そして何よりも手洗いが大事です。アルコール消毒ばかりに頼ってはいませんか?過信は禁物です。アルコールも70%以上のものを手指の全体や隙間にたっぷりと使わなければ効果はありません。できれば、手を洗ってからアルコール消毒の方が全然理想的です。どうしても手を洗えない時や人には有効ですが、それでもたっぷりと時間をかけていると手荒れにも要注意です。あと、まれにアレルギーもあります。
いずれにせよ、コロナ禍はまだまだ続きそうです。どうしても保育園やこども園に通うには体力が心配…という場合は遠慮せずにアイリスにお電話ください。お医者さんがおすすめいただいた場合は、たいていのことは何とかするつもりです。もうすぐ7月です。よい夏にしたいものですね。 |
||
| 手洗い・マスク・アルコール | ||
| 2020/03/23 | ||
|
お彼岸も明け、いよいよ春が近づいてきました。心も体もウキウキして、みんなでどこかにお出かけしたくなってきます……が、今年の春は、例の「新型コロナウイルス感染症」予防のため、あちこちのイベントやテーマパークなどが自粛ムードが漂い、なんとなく気持ちが晴れない日が続いています。
春はいろいろな感染症が流行り出す季節ですが、その多くは「接触感染」「飛沫感染」「空気感染」によるものです。接触感染には手洗いが、飛沫観戦と空気感染にはマスクが、そしてどちらにも有効なのがアルコールで手指や触れる設備や機器等を消毒することが有効とされています。
手洗いは石鹸を使ってできれば20~30秒ほど手指の隅々や手首など丁寧に行うことが大事です。石鹸がない場合でも流水で1分くらい丁寧にこすり洗いすることでかなりのウイルスや菌は流れるといわれています。ですから、感染予防は何よりも「手洗い」に勝るものはありません。
次にアルコール消毒ですが、まず重要なのは「エチルアルコール70%以上」のものであることです。間違ってメチルアルコールや飲用アルコールを使用してはいけません。コロナウイルスはアルコールにとても弱く15秒ほどで死滅するといわれていますから、消毒する際には15秒を目安に乾かないように留意する必要があります。ちなにみ、感染性胃腸炎を引き起こすノロウイルスなどはアルコールでは死滅せず、次亜塩素酸ナトリウムなど次亜塩素系のもの(例:ピューラックス、ミルトン、ハイターなど)を使う必要があります。ただし、これらは肌荒れしやすいことや衣服につくと色落ちすることなどから手指の消毒には不向きなため、どうしても…という場合には、天然食品由来の体に害のないものを選ぶ必要があります。
街にすっかりなくなってしまったマスクはどうでしょう?一般にはマスクを着用すべき人は「病気にかかっている人」(咳のある人、花粉症の人、高血圧やぜんそくなどの基礎疾患のある人を含む)「高齢者や妊婦など感染すると重症化しやすい人」です。健康な人が使用すべきなのは「密集」「密接」「密閉」した場所にいる場合や、調理や看護などで本人の飛沫が相手や対象物に不衛生を与える場合です。基本的には発熱や咳き込んでいる人がいなく、空気の入れ替わりがあり、人がギューギューにいないような場所でのマスクの着用はあまり意味がないと言われています。とはいえ、保育している私たちにとっては、保護者をはじめ世間の目がとても気になるところです。マスクしていることでまわりから安心して見られるような状況は、本来はおかしいのかもしれませんが…。
いずれにしても、一日も早く事態が収束することを祈るのみです。小中学校等の授業再開や入園式・入学式に加え、東京オリンピックもどうなることか?と、心配の尽きない春が始まります。みなさんもご自愛くださいね。 |
||
| 新型コロナウイルス感染症 | ||
| 2020/02/28 | ||
|
新型コロナウイルス感染症が全国各地で感染拡大しています。各地の小中高校の大半は3月から休校となるようですが、保育園や認定こども園は原則として通常通り開園するところがほとんどのようですので、ひとまずご安心ください。 新型コロナウイルス感染症は飛沫感染と接触感染によるとされ、予防には手洗いとアルコール消毒液による手指の消毒が有効と言われていますが、街では2月に入りマスクやアルコール消毒液が品薄となっています。また、今のところ乳幼児は重症化しにくいといわれていますが、高齢者をはじめ基礎疾患のある方や妊婦さんは重症化しやすいため要注意です。
37.5℃以上の発熱、咳、のどの痛み、鼻水などの風邪の症状が4日以上続く、強いだるさがある等の場合は、保健所に相談の上、受診が必要です。特に今の時期はインフルエンザや溶連菌感染症も流行していますので、家庭でもこまめな検温と体調観察を心がけましょう。
ちなみにアイリスでは、新型コロナウイルス感染症の病後の受入れについては、未知の部分が多いこともあり現段階では想定していません。詳しいことが分かり次第、随時この日記でお知らせします。 |
||
| インフルエンザにご用心 | ||
| 2019/12/21 | ||
|
すっかりご無沙汰していました。4ヵ月余りも日記をお届けするのを怠けてしまいまして本当にごめんなさい。
でも、アイリスはしっかりと稼働中です。秋から12月にかけては3日に2日の割合でいろいろなお子さんをお預かりしていました。夏から秋は、りんご病、手足口病(口中に発疹があり食事ができない子)、上気道炎、RS症候群が多く、そしてここ半月前からは、感染性胃腸炎とインフルエンザ(A型)のお子さんの利用が増えています。
特にインフルエンザは、ここ数年は、学校の三学期が始まった1月の半ばから2月いっぱいが流行のピークでしたが、今シーズンは11月頃から県内のあちらこちらで(三八地域→東青地域→弘前地域)広がり出し、西北五地域では12月に入ってぐんと増えてきています。
とはいっても、全体的な流行の傾向は「スポット的」であることです。つまり、例えば五所川原市内では、小学校や保育園などで流行っているところとそうでないところに偏りがあることです。アイリスの運営母体の施設であるみどりの風こども園ひろたでは、171人の園児のうちインフルエンザ罹患児は、今季の累計で6名と全体のわずか3.5%ですが、某園では40%超にも上っているところもあるようです。また、みどりの風こども園ひろたは、栄小学校の学区に属しますが、この栄小学校をはじめ三輪小学校でも、ここ2~3週間で20%ほどの罹患率となっています。
このように、今回のインフルエンザは流行にバラツキがあることが特徴のようですが、用心に越したことはありません。これからクリスマスやお正月など楽しい行事が目白押しです。年末年始のお休みもあります。でも、そのぶん、感染者と遭遇したり接触したりする確率が高くなりますので、マスクの着用とこまめな手洗い、上着の着脱・保管等には十分に気を付けたいものです。
インフルエンザに罹ってしまった場合、アイリスは熱が下がって24時間経過した日から2~3日間の利用可能となります。何度も通院することも面倒でしょうから、インフルエンザだと診断された時点で「医師連絡票」を書いてもらうことをお勧めします。ただし、年末年始と土日、そして看護師が出張等の日はアイリスはお休みとなりますので、前もってご了承ください。ちなみに、今年は12月27日(金)までお子さんをお受けします。新年は1月6日(月)から再開いたします。
それでは、楽しい年末年始をお過ごしください。 |
||